フィンランディアの楽譜を見て、前から気になっていたことがあります。
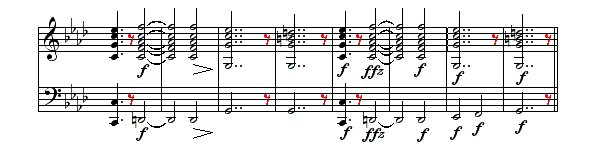
曲の前半部分は長い音符が多いのですが、その最後のほうになってくると、音符のあとに八分音符が書かれています。
これが、「最後までちゃんと延ばしなさいよ!」という警告に思えてくるのです。
・・・そんなこと言うなら、休符がないほうがいいんじゃないの?
いえいえ、これらが全音符や二分音符だったりしたら、楽譜から受けるイメージは違ったものになってくるでしょう。
弦楽器はどんなボウイングで弾くのでしょう?
この八分音符の瞬間に弓を弦から離すことによって、次の音へのエネルギー源になるのでは?
延ばす音符が力のこもったものになるのでは?
意味はどうであれ、書いてあることは事実。
しかも、わざわざ書いているのです。
これを見ると、チャイコフスキーの細かい音符も思い出します。
もちろん、ブラームスも。
ブラ1の1楽章では、1拍目にあたる音にはいろいろなものがあることがわかります。
出てくるもん順に、
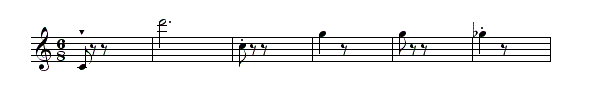
ブラームスが書いた仕掛けをもっともっと読み解く必要があるようです。
(シベリウス/交響詩フィンランディア 過去の演奏会では:1988年など多数)